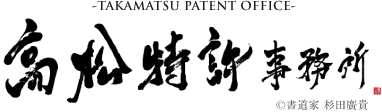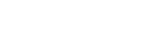今回は、非常によく受ける特許相談についてです。
相談内容として「こういう発明をしたけど特許にならないか?」が挙げられます。相談者側からすれば最も気になる点ですし、高い費用をかけなければならないので無理もありません。
発明の内容が明らかに公知技術(例えば「容器本体に取手を設けたコップ」)であれば、「新規性がないため特許は難しい」と回答できます。しかしながらこのように回答できるケースは少なく、悩むことの方が多いです。そのため、相談の席では「特許調査を行わなければ分からない」、「特許出願を行って審査を受けた方がよい」という無難な回答に終始してしまいがちです。
上述のような回答ではあまりにも芸がありませんので、専門的な回答をするのであれば、「特許になるかならないかは、「特許請求の範囲」の書き方によって変わってくる」ということになります。
すなわち、我々弁理士は発明のポイントを見定め、そのポイントを基に特許請求の範囲を考えます。権利範囲は広いに越したことはないので、出来るだけ広い表現を模索します。併せて、限定可能な構成要件についても検討します。
実務上は、下記のように独立項(請求項1)に複数の従属項(請求項2,3)を従属させる方法が多くとられます。
(請求項1)AとBを備えた○○装置。
(請求項2)Cをさらに備えた請求項1記載の○○装置。
(請求項3)Dをさらに備えた請求項2に記載の○○装置。
請求項2をより分かりやすく表すと、「AとBとCを備えた○○装置」となります。
請求項3をより分かりやすく表すと、「AとBとCとDを備えた○○装置」となります。
権利範囲が最も広いのは請求項1で、次に広いのは請求項2、最も小さいのは請求項3となります。すなわち、構成要件(A~D)が少ないほど権利範囲は広くなり、構成要件が多くなるほど権利範囲は小さくなります。但し、構成要件が多くなることによって特許になる可能性は高くなります。
このように、我々弁理士は特許請求の範囲を戦略的に練り、特許になるかならないかのギリギリのラインを求めていきます。
結論として、限定可能な引き出しの数が多ければ多いほど、特許になる可能性は高くなる傾向にあります。もっとも、その引き出しが公知技術ではないことが重要です。